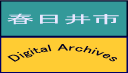 「おまんとう」作り風景
「おまんとう」作り風景春日井市高蔵寺町内
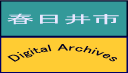 「おまんとう」作り風景
「おまんとう」作り風景
| 毎年梅雨の終わりの頃、高蔵寺地区区内、各町内で 「おまんと」のだし作りが朝早くから始まります。これは 町内の住民全員が参加して子どもたちが担ぐ「だし」 作りの記録です。 |

|
 竹の先端方を切り取り太い方の2節を8つに切り分け、別の竹で作った 直径約20cmくらいの竹輪をその中へ入れ先端を中へ折り曲げる。 |
 竹の根元の太いところを選んで節を残して一節分の長さに切り、節の側に吹き口となる穴を 開けるこの竹笛を吹くと低い音でぼぉ〜と鳴る。 子どもたちがこの笛を吹き鳴らしながら町内を歩いたといわれています。 |
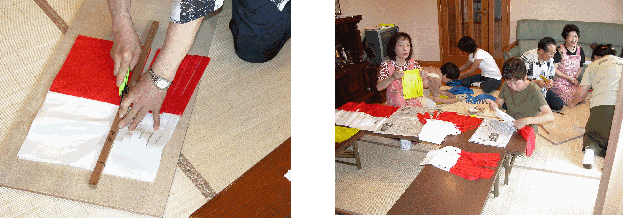 、「だし」の一番上に紅白の紙を付けます、白一枚に赤二枚を張り合わせます。 そして赤い方に短冊形に切込みを入れます。白は雲を、赤は太陽を表すとも言われています。 |
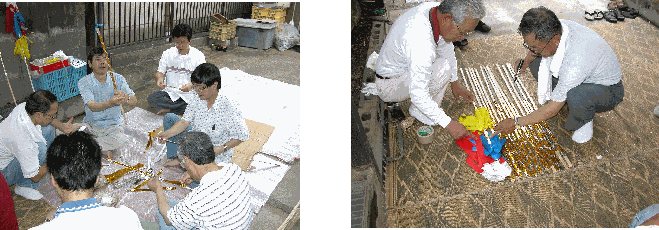 削り終えた「だし」に金と銀の紙を細く切ったテープを巻きつける。 前年のものを参考に短冊を付ける位置を決めて印を付ける.。 |
 一番上が白と赤の短冊、次に青、一番下が黄で、それぞれ糊付けして麻紐で縛る。 |
 麻で縄を編む(毎年新しく作る) 「だし」の高さを揃えながら芯に麻縄で縛り取り付ける。 |
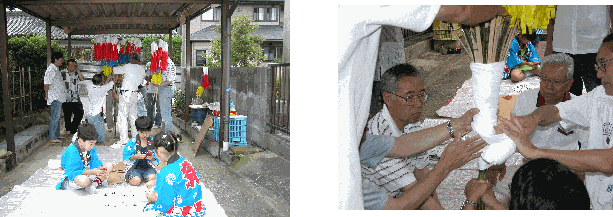 「だし」を一本ずつ芯に縛り付けて最後に子どもが肩に担いでも痛くならないように新聞紙を下地の巻いてその上から一反の木綿布を巻きつける、この木綿布は祭が済んで解体したときに最年長の子どもに与えられます。 |
 子どもたちが「だし」を担いで神社へ行きお払いを受けて、町内へ戻り「わっしょい、わっしょい」 の掛け声で一軒一軒回り祝儀を受け取る。その祝儀は年長の子どもがみんなに分け与える という習慣があります。 |
| 大人たちの一日 この「だし」作りはその年の常会長の家で行います。 町内全員が参加して「だし」をつくり、作り終えると昼食を兼ねた懇親会が始まります。 子どもたちには常会長と互長(2名)が付き添って神社へ行きます。 その間もずっと懇親会は続きます。 子どもたちは神社から帰ってきて町内を回ってくると「だし」を分解して、大人たちがそれぞれの家へ一本ずつ持って帰り一日が終わります。 2003/7/13 |